インフォメーション
キャンペーン
-

SUBARU初売りフェア2026
フェア期間中、ご来店で特別なプレゼントが当たる新春おみくじ大抽選会を開催。
-

新車購入資金プレゼントキャンペーン
この冬、SUBARUから特別なチャンス!
2025年12月25日(木)〜2026年2月15日(日)まで、SUBARU普通乗用車をご検討の皆さまを対象に実施中。 -
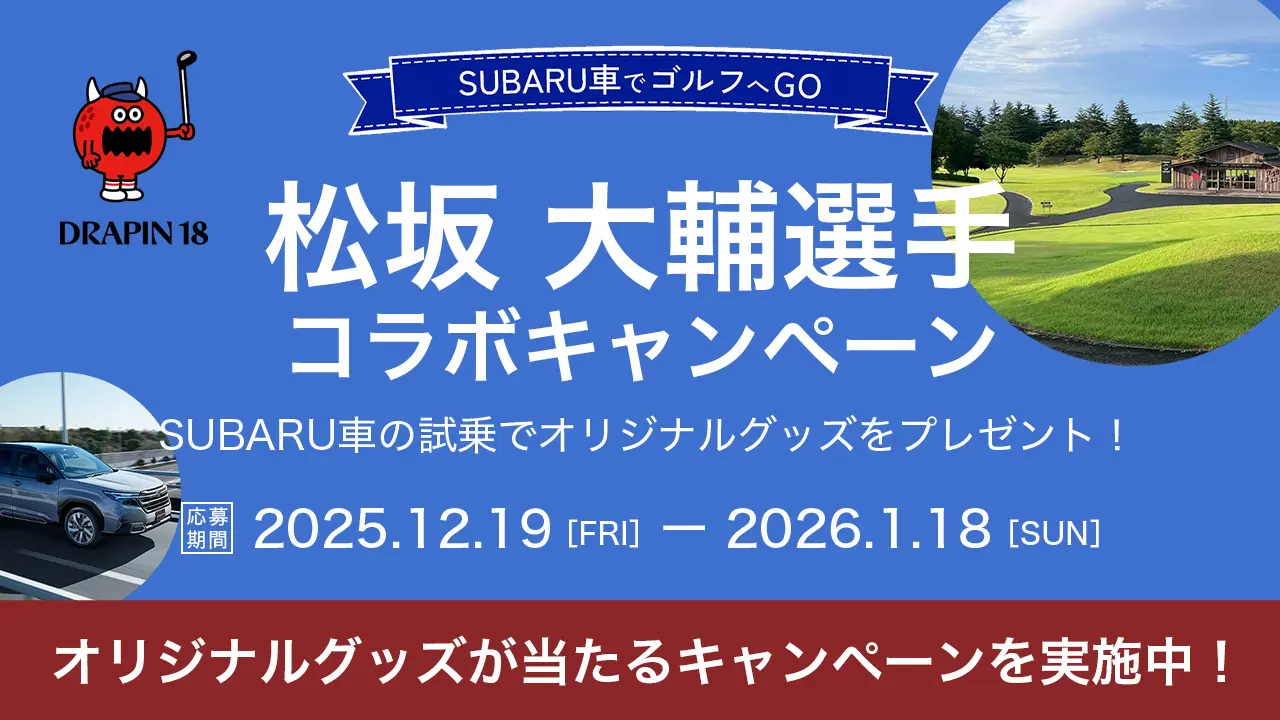
松坂大輔選手コラボキャンペーン
SUBARU車の試乗いただくと、抽選でオリジナルグッズをプレゼント!
-

BEV LIFE
スタートアップキャンペーンSUBARUのBEVご成約で最大10万円相当の選べる特典。家庭用充電器かデジタルギフトが当たる!
-

大切な家族を守りたい、
安全で選ぶならクロストレック!妊娠中の方や子育て中のパパ・ママへ。大切な家族を守るため、安全性能を最優先にした車選びを。
-

SUBARU スタートアップキャンペーン
インプレッサ・クロストレックのご成約で、
今ならナビタダ! -

コンパクト&軽ラインアップ
REX・JUSTYを「残価設定型クレジット」でご成約の方へ。特別なプレゼントをご用意。
-

WEB試乗予約キャンペーン
WEB予約+店頭試乗で毎週10名様に1万円相当のデジタルギフトをプレゼント。
SUBARUの取り組み
-

東京オートサロン2026
東京オートサロン2026(TOKYO AUTO SALON 2026) のSUBARU/STIブース出展情報はこちら!
-
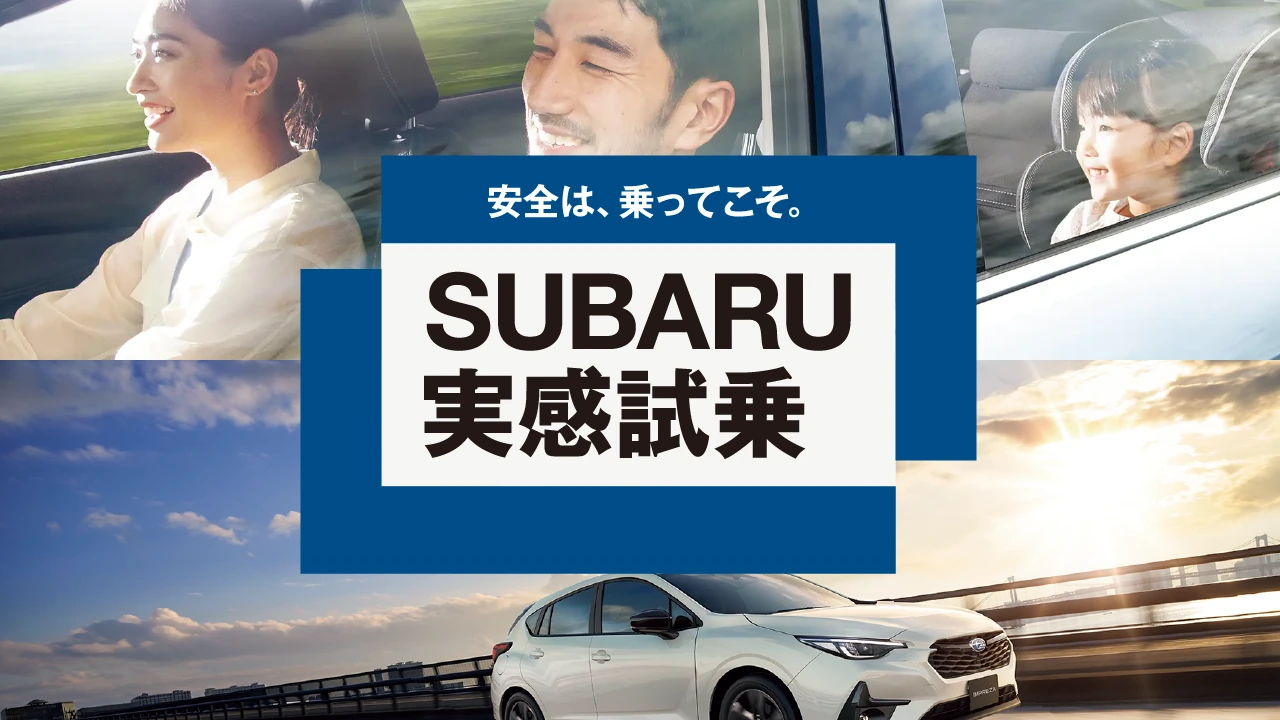
SUBARU実感試乗
SUBARUが航空機メーカーの時代から受け継ぐ設計思想を反映した4つの安全ポイントを、ぜひ試乗で実感してください。
-

SUBARU × SAJ
50周年記念コラボサイトSUBARU と全日本スキー連盟(SAJ)は、2026年に協賛50周年を迎えます。共に力を合わせて雪に挑んできた歴史を記念して、SAJとスペシャルコラボ企画を実施します!
-

ゲレンデタクシー
スキーやスノーボードを愉しむ皆様を乗せて、SUBARU車が雪山を駆け上がる体験型イベント。2026年は群馬県パルコール嬬恋リゾートで実施決定。2026年1/31(土)、2/1(日)、2/7(土)、2/8(日)お待ちしております。
-

一つのいのちプロジェクト
いのちを守ることを大切にしてきたSUBARU。
その想いを同じくするパートナーたちと一緒に取り組んでいきます。 -

SUBARUモータースポーツ
スバルの参戦する世界のモータースポーツ情報。
最新ニュースを配信します。
トピックス
-

雪道を走るならSUBARU
雪道は怖いから、あんまり運転したくない…。その心配、わかります。でも大丈夫!SUBARUなら、雪道だって安心して運転できますよ!
-

フォレスター試乗会レポート
各メディアが参加した試乗会でも好評を博したフォレスターの走りを、試乗で体感!
-

SUBARU×KINTO
月々定額で新車に乗れる!維持に必要な維持費がコミコミで新車に乗れるサービスです。
-

SUBARUの残価設定型クレジット
ライフステージの変化に合わせて、
最新のSUBARU車に乗れるクルマの買い方です。 -

中古車ならスグダス
豊富なラインアップからお客様のご希望にピッタリの一台をお選びいただくことができます。
-

SUBARUのサポカー
クルマを運転する全てのドライバーに安心・安全のカーライフを提供していきます。
-

SUBARUのエコカー減税
エコカー減税対象車をご紹介。エコカー減税制度や優れた環境技術などをご紹介しています。
-

WEBカートピア
SUBARUの魅力や最新情報、SUBARUと過ごすカーライフの愉しさをお届けするメディアです。
-

SUBAROAD
走る道のすべてを発見と刺激へナビゲートするSUBARUオーナーのためのドライブアプリ。
-

スバルスタースクエア
(恵比寿ショールーム)東京・恵比寿にあるスバルの本社ショールームをご紹介します。
-

SUBARUオンラインショップ
スバルとSTIの公式ウェア&グッズが買えるSUBARUオンラインショップです。ここでしか買えない限定商品を取り揃えています。
-
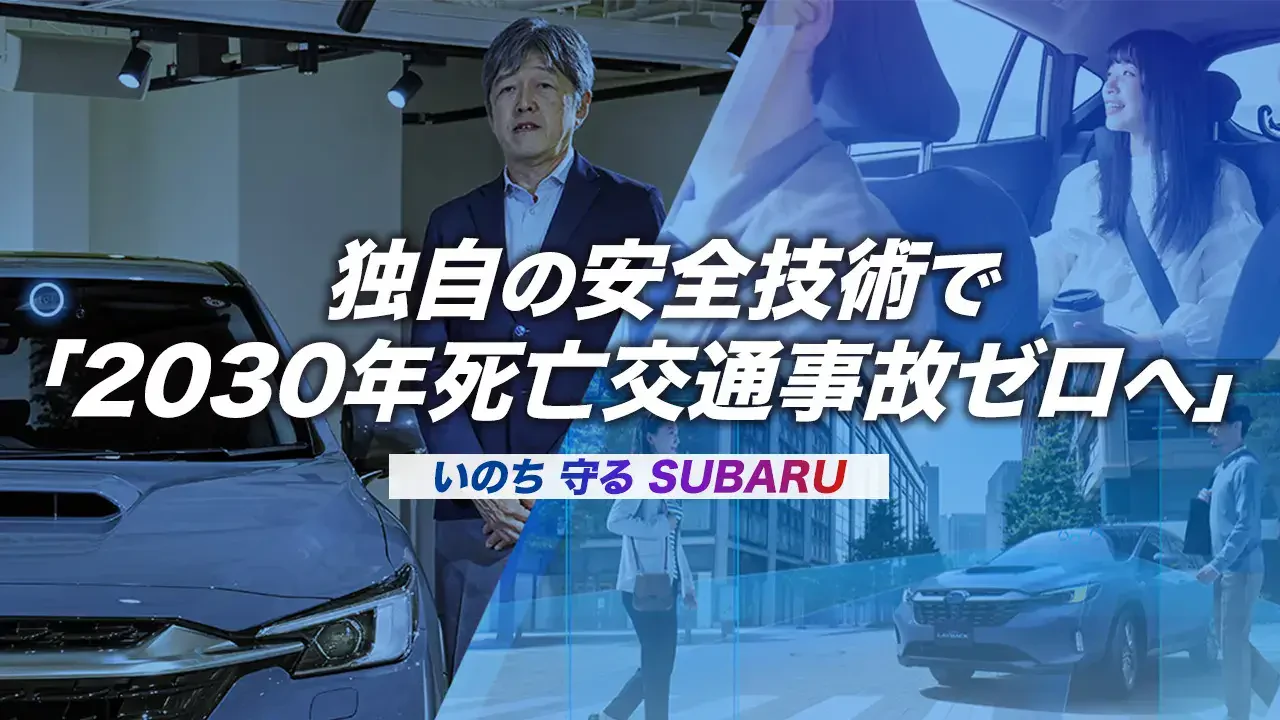
2030年死亡交通事故ゼロへ
アイサイト開発をけん引してきた柴田英司CDCOが語ります。
-

アイサイト体感試乗チャレンジ
SUBARUの“ぶつからない!?“をサポートする技術を体感!店頭やイベントで好評実施中。
-

愛犬とお出かけするならSUBARU
過ごしやすい空間と走りの性能があるから、愛犬も快適にドライブを愉しめます。
-

アウトドアアクティビティなら
クロストレックアウトドアアクティビティに適しているポイントをご紹介します。
-

安全の原点は飛行機づくり
「絶対に事故を起こさせない」という安全思想と「搭乗者の安全を守る」技術がモノづくりの根底にあったのです。
-

SUBARUのSUVで
アクティビティに出かけよう!様々なアウトドアライフにぴったりなSUBARUのSUVをご紹介します。
-

ヒヤッとすることが増えたあなたにもSUBARUのクルマで安心を届けたい
昔よりも運転中にヒヤッとすることが増えて不安を感じるそんなあなたへ、SUBARUのこだわりが安心感をお届けします!
-

レイバックの新CMロケ地
@釧路の絶景を巡る篇CMロケ地・釧路の絶景を舞台にした試乗会。
その空気感とドライブ体験をお届けします。 -

レヴォーグでSUBAROAD新コース
@群馬を駆ける篇いち早く新コースを体験した参加者のリアルな声を、ぜひご覧ください。
-

SUBARU SPORT
安全・快適なクルマは、速く、愉しく走れる。
これは、SUBARUの「安心と愉しさ」の源となるフィロソフィーです。 -

STI Advanced Oil
世界のモータースポーツで戦うSTIが選んだSUBARU純正エンジンオイル。ワンランク上の
エンジンフィーリングを体感できます。 -

日本の原動力、軽自動車。
軽自動車の有用性が女性の社会進出を支え、高齢者の足となり、地方のインフラとして支える。そんな軽自動車は、みんなの頼りになる車です。
ニュース
- 2025.11.13 更新情報 SUBARU BRZ 特別仕様車 TYPE RA登場(特設サイトへ)
- 2025.10.31 更新情報 SUBARU STARLINKは「MySubaru Connect」へ名称を変更しました(詳細ページへ)
- 2025.10.30 更新情報 クロストレック 特別仕様車 WILDERNESS Edition登場(特設サイトへ)
- 2025.10.15 更新情報 新型ソルテラ登場(カタログサイトへ)
- 2025.09.05 更新情報 SUBARU BRZ 特別仕様車 YELLOW EDITION登場(カタログサイトへ)
- 2025.07.24 更新情報 フォレスター特別仕様車 Black Selection登場(カタログサイトへ)
- 2025.06.12 更新情報 新型レックス登場(カタログサイトへ)
- 2025.06.12 更新情報 新型ステラ登場(カタログサイトへ)
- 2025.04.17 更新情報 新型フォレスター登場(カタログサイトへ)
- 2025.01.16 更新情報 新型ソルテラ登場(カタログサイトへ)
- 2024.12.12 更新情報 新型レイバック登場(カタログサイトへ)
- 2024.12.12 更新情報 新型レヴォーグ登場(カタログサイトへ)
- 2024.12.12 更新情報 新型WRX S4登場(カタログサイトへ)
- 2024.12.12 更新情報 新型ジャスティ登場(カタログサイトへ)
- 2024.12.05 更新情報 新型クロストレック ストロングハイブリッド登場(カタログサイトへ)
- 2024.11.07 更新情報 初代レガシィ「2024 日本自動車殿堂 歴史遺産車」に選定(ニュースリリースへ)
- 2024.11.07 更新情報 新型レックス登場(カタログサイトへ)
- 2024.11.07 更新情報 新型サンバーバン登場(カタログサイトへ)

