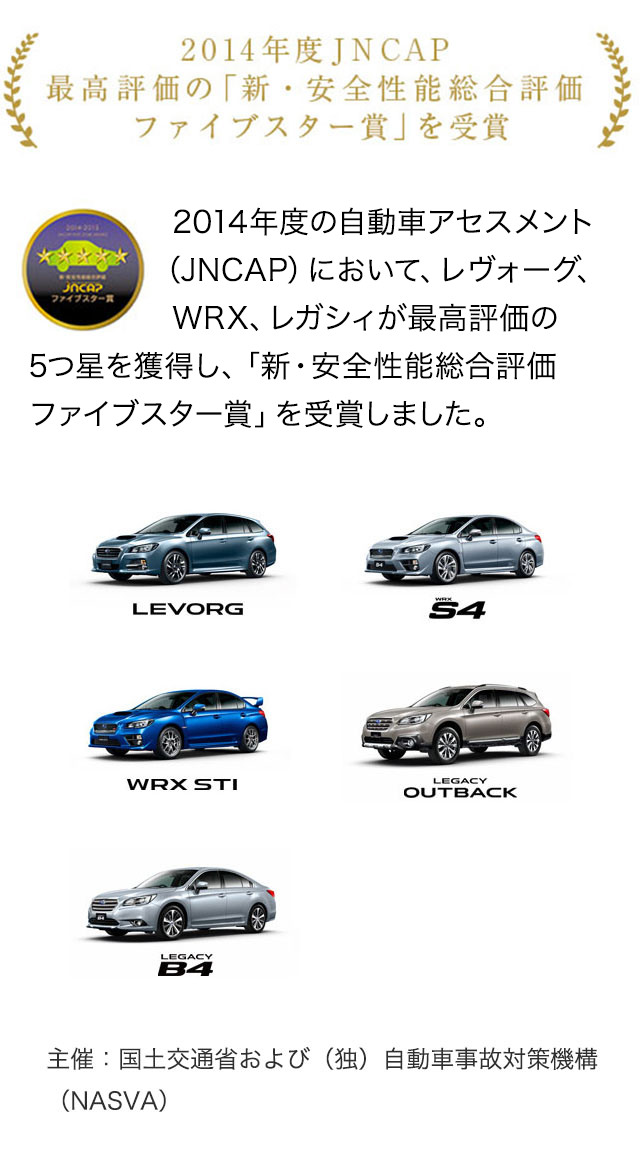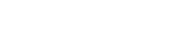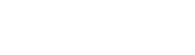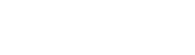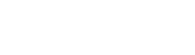WRX S4

メーカー希望
小売価格4,477,000円(税込)〜
月々15,800円から お支払い例はこちら
WRX S4のお支払い例
愉しさも安心も、お届けしたいから。
月々のお支払い額を抑えて、
安心のカーライフを送っていただけるプランを
ご用意しました。
たとえば月々
15,800円から乗れます。
| グレード | GT-H EX |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 (消費税10%込) |
4,477,000円 |
| クレジットプラン | 残価設定型 (ボーナス併用) |
| お支払い回数 | 58回 |
| 実質年率 | 3.9% |
| 頭金 | 1,277,000円 |
| 所要資金 | 3,200,000円 |
| 初回お支払い額 | 17,544円 |
|---|---|
| 月々お支払い額 | 15,800円 |
| ボーナス加算額 | 94,000円 × 10回 |
| 最終回お支払い額 | 1,831,000円 |
| お支払い総額 | 4,950,344円 |
今なら試乗で100人に1人
1万円分のポイントが当たる!
WRX S408の特徴
01 普段の街中からスポーツ走行まで、いつでも思いのままの走りを愉しめる。
力強いパフォーマンスを発揮する2.4L直噴ターボエンジンにより、誰もが愉しく過ごせる走行性能を備えています。
02 まるで熟練ドライバーが操作するMTのような変速感覚。
SUBARU最新の自動無段変速機「スバルパフォーマンストランスミッション」を採用し、素早い変速スピード、キレのある変速感覚を実現しました。
03
アグレッシブな個性と機能性を併せ持つ
エクステリアデザイン。
見た瞬間に走りへの期待を駆り立て、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを感じられるデザインを目指しました。
04
スポーティに洗練されたデザインと身体を包み込む
一体感が、走りへの期待感を高める。

スポーティさと先進性をあわせ持ったWRX S4ならではのデザインを追求しました。
05 STI Sport独自の機能と質感で、刺激的な走りを味わえる。
走りの特性を選べるドライブモードセレクトやボルドーの内装などが気持ちを高めます。
06 自分の思った通りに反応してくれて、乗り心地も快適。
ハンドリングの良さと、それに背反する乗り心地や快適性、静粛性を一切犠牲にすることなく、高いレベルで両立しました。
07 3つのカメラでいのちを守る、最新のアイサイト。
アイサイト搭載車*は、
追突事故発生率
[
%
]
SUBARU車1万台あたりの
追突事故件数
追突事故発生率
2010-14年
0.56%
アイサイト(ver.2)
非搭載車
2010-14年
0.09%
アイサイト(ver.2)
搭載車
2014-18年
0.06%
アイサイト(ver.3)
搭載車
公益財団法人・交通事故総合分析センター(ITARDA)のデータを基に独自算出
*2014-18年 アイサイト(ver.3)搭載車

08 GPSや衛星情報のアシストで、高速道路の渋滞も安心。
渋滞時のハンズオフ走行やカーブ前の速度制御などの機能で、運転の負荷を軽減します。